親の不動産管理の具体的な管理方法
※このサイトは(一社)全国幸せ相続計画ネットワークをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
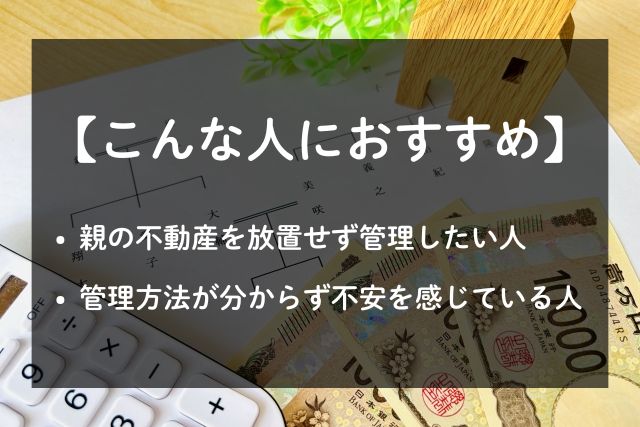
親の不動産、今後どうすればいいのか不安に感じていませんか?放置すれば老朽化や空き家リスク、相続トラブルにもつながります。
この記事では、親が元気なうちにやっておきたい不動産管理のポイントを、相続の専門家がわかりやすく解説します。
- 親が元気なうちから不動産管理を始めることが重要
- 不動産管理を怠ると、老朽化や税金リスク、相続トラブルの原因に
- 管理方法には名義確認、利用状況の把握、定期的なメンテナンスなどがある
- 管理に不安がある場合は、専門家への相談が早期解決のカギになる
sponsored by
親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
その代表理事であり、業界唯一の特許※を取得した相続対策の第一人者が亀島 淳一さんです。
「家族をもめさせない」「財産を減らさない」「子や孫をお金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・山口県・北九州市・熊本県・沖縄県
上記エリア外でも、ご相談内容に応じて柔軟に対応可能です。
親の不動産管理が
必要な理由
高齢化による管理不全リスク
不動産の所有者である親が高齢になると、認知症による管理不全リスクが起こります。認知症と診断されると不動産を本人の意思で管理・売却することが難しくなり、いざというときに現金化できないという状況に陥ります。
そのような事態に備えて、任意後見人を選定したり、家族信託を利用することで、親の不動産を家族が管理する体制を作ることができます。
相続時に発覚する問題を
事前に防ぐ
親の不動産管理を生前から行っておくことは、相続時のトラブルを事前に防ぐことにもつながります。あらかじめ財産の内容を把握することで、相続時に起こりうるリスクの洗い出しや、分配方法について事前に話し合うことができます。
さらに節税対策にも目を向けられるので、財産を有効的に活用できます。
資産価値を維持・向上するには
親の不動産の価値を維持・向上するには、資産の組み換えを検討しましょう。収益性が低く維持コストのかかる“負動産”を売却し、その資金で優良財産に買い換えることで資産価値が向上します。
古いアパートを処分して駅近に新しいアパートを建てたり、建物を土地に買い換えるといった方法も資産の組み換えにあたります。
まず確認すべき親の
不動産の情報
名義・登記情報を調べる
親の不動産を管理するには、まず不動産の名義を調べます。不動産の所有者を示す名義は、登記簿謄本によって確認できます。登記簿謄本は、法務局で誰でも取得することが可能です。
相続による名義人変更(相続登記)は2024年に義務化されましたが、以前は名義人が亡くなったにもかかわらず変更手続きされないケースが多かったため、現在の登記情報を確認することは重要です。
利用状況・現況の把握
次に、親が所有している不動産の現況を把握しましょう。自宅として利用しているもののほかにも、賃貸物件や貸地、空き家、空地などのケースが考えられます。賃貸物件や貸地の場合は、賃借人との調整が必要なので、すぐに処分することができません。
また、所有する不動産が「空き家特例」の指定空き家に該当する場合、相続後に最大6倍の固定資産税を課される可能性があるため注意が必要です。
将来的な利用予定を確認する
不動産の現況が分かったら、将来的な利用予定を親と相続人同士で話し合います。両親が亡くなったあとは長男が家族で住む、賃貸に転用する、家屋を取り壊すなどのプランについて話し合っておくことで、相続時にもめることなく円滑に決定することができます。
具体的な管理方法と
ポイント
定期的な清掃・修繕の実施
家屋は人が住んでいてもいなくても、定期的なメンテナンスが必要です。外壁の清掃や屋根の葺き替え、リフォームやリノベーション、設備の修繕など、メンテナンスによって建物を良好な状態に保つことで、不動産の価値を維持・向上させることができます。
保険・税金の見直し
相続時の税金の負担を減らすためには、課税対象を減らす保険・税金の見直しが有効です。①生前贈与で親の不動産そのものを減らす②不動産の組み換え購入で財産の評価額を下げる③生命保険に加入して死亡保険金に対する相続税の非課税枠を活用、などの方法が考えられます。
不動産管理会社への委託も検討
賃貸物件の場合は、不動産管理会社へ委託することで管理の負担を減らすことができます。プロの管理により、賃貸借契約、入居者対応などを任せることができます。
委託料は家賃の5%ほどですが、空室でも支払うケースがあるため、現在の稼働率や立地条件などを加味し、依頼前に慎重に検討しましょう。
管理を通して備える
相続・売却対策
相続税対策としての不動産管理
不動産を貸家建付地にすると、相続税評価額は更地の場合よりも低くなります。その建物を他人に貸している場合は、借家権割合(通常30%)に応じた評価減が適用されます。
そのため、不動産を賃貸用物件にして管理・運用することは、家賃収入に加えて相続税の節税効果の面でも大きなメリットとなります。
売却・活用の判断材料としての
管理
不動産の売却・活用を判断する上で、不動産管理によって得られる情報は重要です。空室率、家賃相場、修繕費、管理費、税金などを総合的に考慮することで、物件の収益性や維持コスト、リスクなど物件の資産価値を判断することができます。

資産価値を下げない
管理が相続では重要
親の不動産を将来にわたって守るには、資産(収益)価値を下げない管理が重要です。定期的な修繕や家賃の見直し、収支や空室状況の把握などを行うことで、適正な収益性を維持し、相続時にも有利な状態を保てます。
つまり、資産(収益)価値を下げずに次の世代に引き継ぐことができるということです。
sponsored by
幸せな相続をサポートする
全国幸せ相続計画
ネットワークが監修
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。
社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得※した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
※対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・山口県・北九州市・熊本県・沖縄県
上記エリア外でも、ご相談内容に応じて柔軟に対応可能です。
